
感染すると耳の下(耳下腺)が腫れて痛んだり、熱が出たりするおたふくかぜは、重症化すると難聴になるおそれもある怖い感染症です。
しかし、ワクチンを接種すれば発症する確率を大幅に下げることができます。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)の接種を考えている人のなかには、「ワクチン接種にどんなメリットがあるの?」「接種すると本当に発症しなくなるの?」など疑問や不安を抱いている人もいるでしょう。
本記事では、おたふくかぜワクチンを接種するメリットとその費用、接種のタイミングを解説します。
おたふくかぜワクチンの概要やよくある質問についても解説しますので、予防接種を受けるかどうか決める際の参考にしてください。
目次
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)は何を予防するワクチン?

おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)は、おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)の発症を予防するためのワクチンです。
おたふくかぜはムンプスウイルスによって引き起こされる感染症で、発症すると以下のような症状が現れます。
- 発熱
- 唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)の腫れ・痛み
重症化すると髄膜炎や難聴、脳炎を発症することもあるため、ワクチンによって発症・重症化を予防することが大切です。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)は定期接種?任意接種?
以下で、おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)の概要をお伝えします。
- おたふくかぜワクチンの接種は任意
- おたふくかぜワクチンを接種する時期
- おたふくかぜワクチンの接種にかかる費用
おたふくかぜワクチンの接種は任意
おたふくかぜワクチンは、任意接種のワクチンです。
予防接種は、予防接種法に基づく定期接種と、状況に応じて接種する任意接種に分けられます。
定期接種が誰もが受けるべき予防接種であるのに対し、任意接種は個人の意思で受けるかどうか決める予防接種です。
おたふくかぜワクチンと同じ任意接種の予防接種には、季節性インフルエンザワクチンなどがあります。
おたふくかぜワクチンを接種する時期
おたふくかぜワクチンの接種が望ましいとされる時期は、次の2回です。
- 1回目:1歳になったとき
- 2回目:小学校入学前の1年間の間
1回の予防接種では免疫が十分につかないため、日本小児科学会は2回の接種を推奨しています。
おたふくかぜワクチンの接種にかかる費用
おたふくかぜワクチンの接種にかかる費用は病院によって異なりますが、1回あたり4,000〜6,000円のところが多いでしょう。
公費による助成を行っている自治体もあり、無料で受けられる場合もあります。
助成費用や対象となる子どもの年齢は自治体によって異なるので、厚生労働省または自治体のサイトで確認してください。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)を接種するメリット

おたふくかぜワクチンを接種するメリットは次の3つです。
- 重症化してムンプス難聴になるのを防げる
- 重症化して髄膜炎や脳炎・膵炎などの合併症を起こすのを防げる
- 耳の下(耳下腺)の腫れが軽くなる
重症化がどのくらい抑えられるかは個人差があります。しかし、ワクチンを接種すれば、接種しないときに比べて症状が軽く済み、発症する可能性自体も低くなります。
重症化してムンプス難聴になるのを防げる
ムンプス難聴とは、おたふくかぜ患者のおよそ1,000人に1人がかかるという急性の難聴です。おたふくかぜが重症化すると発症することがあります。
ムンプス難聴になった場合、ステロイドなどを利用して治療しますが、完全に聴覚を取り戻すのは難しいとされています。
ムンプス難聴を防ぐには、おたふくかぜワクチン接種が有効です。
おたふくかぜワクチンを接種することにした国では、1回接種で88%、2回接種で99%発症者数が減少したといいます。
重症化して髄膜炎・脳炎・膵炎などの合併症を起こすのを防げる
おたふくかぜが重症化すると、脳炎を発症することがあります。脳に炎症が起きることで、障害や後遺症が残ることも少なくありません。
また、おたふくかぜになると50人に1人の割合で無菌性髄膜炎を発症します。無菌性髄膜炎は、発熱・頭痛・嘔吐の3症状が見られる髄膜の炎症です。
ただし、合併症や後遺症が残ることはほとんどありません。
ほかにも膵炎や腎炎などを引き起こすことがあり、思春期以降になると精巣炎や卵巣炎を発症するケースもあります。
耳の下(耳下腺)の腫れが軽くなる
おたふくかぜに感染すると、両方またはどちらかの耳の下(耳下腺)が腫れ、痛みが出てきます。腫れた耳下腺は、唾液の分泌に伴って痛むのが特徴です。
おたふくかぜによる耳下腺の腫れには、特効薬がありません。症状に合わせて対症療法的に薬を服用し、症状が軽快するまで待つしかないのが現状です。回復まで1~2週間程度かかります。
2回ワクチンを接種していればほぼ発症を防げるので、仮にムンプスウイルスに感染したとしても耳下腺の腫れや発熱といった症状は出ないか、出ても軽症で済むでしょう。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)を接種するデメリット
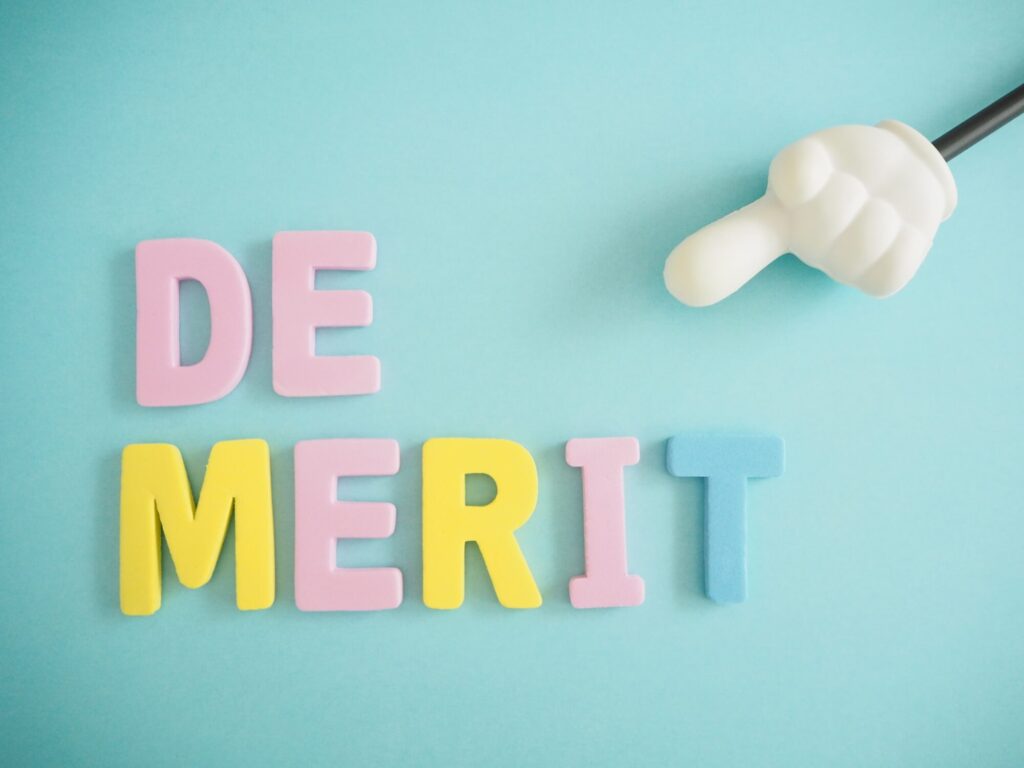
おたふくかぜワクチンには、メリットだけでなくデメリットもあります。主なデメリットは次の4つです。
- 接種から10~14日後に微熱が出たり耳下腺や頬が腫れたりする
- 接種後3週間ほどして無菌性髄膜炎を発症することがある(40,000接種あたり1回の割合)
- アナフィラキシー反応が起こることがある
- 難聴や精巣炎、血小板減少性紫斑病になることがある
いずれも、かなり稀なケースであり、また仮に症状が出たとしてもおたふくかぜに感染した場合よりは症状が軽く済みます。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)を接種できない人
おたふくかぜワクチンが接種できないのは、次のような人です。
- 明らかに発熱している人
- 重い急性疾患にかかっている人
- ワクチン接種でアナフィラキシーを起こしたことがある人
- 免疫機能に異常がある人
- 免疫抑制剤などを服用している人
- その他、医師が接種すべきでないと判断した人
心臓や腎臓・肝臓・血管・血液に持病がある人や、これまでの予防接種で体調を崩したことがある人は、接種前に医師とよく相談することが大切です。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)に関するよくある質問

おたふくかぜワクチンに関するよくある質問をまとめました。
- おたふくかぜワクチンを接種すれば、おたふくかぜにかからない?
- 2回目の接種を受け忘れたけど、数年後でも接種させた方が良い?
- 他のワクチンを接種してから何日くらい空ければ接種できる?
- ワクチンを接種したか、おたふくかぜにかかったかわからない場合はどうすれば良い?
- 大人になってからおたふくかぜにかかると子どもが持てなくなるというのは本当?
接種するかどうかを決める際の参考にしてください。
おたふくかぜワクチンを接種すれば、もうおたふくかぜにかかりませんか?
おたふくかぜワクチンには、発症予防効果があります。しかし、発症を予防することはできてもムンプスウイルスへの感染を予防することはできません。
ワクチンを打ったからといって油断せず、身近におたふくかぜにかかった人がいるときはしっかり手洗い・うがいをして感染症対策を行いましょう。
2回目を受けるのを忘れ、数年経過してしまいました。今からでも接種させた方が良いですか?
1回目の接種から時間がたっている場合でも、2回目のワクチンを接種することは可能です。
ワクチンを2回接種すれば発症予防効果はより高まるので、まずはかかりつけの医師に相談してみましょう。
他のワクチンを接種してから、どれくらい間を空けたら接種可能ですか?
接種したワクチンの種類によって、空けなければならない間隔が異なります。おたふくかぜワクチンを接種する前に生ワクチンを接種したときは間隔を空けなくてはなりません。
経口生ワクチン・不活化ワクチンの場合は、間を空けずに接種してかまいません。
経口生ワクチン・不活化ワクチンには、
- ロタウイルスワクチン
- ヒブワクチン
- 小児用肺炎球菌ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- 4種混合ワクチン
などがあります。
生ワクチンの場合は、接種後27日以上空けましょう。
生ワクチンには、
- 麻しん風しん混合ワクチン
- 水痘ワクチン
- BCGワクチン
などがあります。
大人です。子どもの頃ワクチンを接種したか、また、おたふくかぜに罹患したかがわかりません。
子どもの頃おたふくかぜワクチンを接種したか覚えていない場合や、おたふくかぜに感染したかわからない場合は、抗体検査を受けましょう。
血液を採取して調べれば、おたふくかぜの抗体を持っているかどうかがわかります。
抗体検査は、内科または小児科で受けられます。詳しくはかかりつけの医療機関に問い合わせてください。
ワクチンを接種せず、大人になってからおたふくかぜになると子どもが持てなくなると聞きました。本当ですか?
思春期以降におたふくかぜを発症すると、精巣炎や卵巣炎が起こりやすくなります。また、妊娠早期に感染すると、流産のリスクが高まります。
大人になってから発症すると子どもが持てなくなるとは限りませんが、不妊・流産のリスクが高くなるのは事実です。
おたふくかぜワクチン(ムンプスワクチン)の接種はメリット多数
おたふくかぜには特効薬がないため、発症してしまったら対症療法で様子を見ながら自然に治るのを待つしかありません。
重篤な合併症を引き起こすケースもあるので、できるだけ予防に努めましょう。
おたふくかぜの予防には、2回のワクチン接種が有効です。
おたふくかぜワクチンの接種を検討している人は、かかりつけの医療機関で相談してみましょう。

監修医師
古東麻悠(ことう・まゆ)
順天堂大学医学部卒業。途上国医療に関心を持ち、学生時代よりアジア・アフリカ各国の保健指導、巡回診療に参画。子どもたちのトータルサポートを目指し、小児科医として働きながらNPO法人very50、NPO法人Ubdobe(現株式会社デジリハ)のメディカルアドバイザーを兼務。現在は都内総合周産期病院にて新生児科医として勤務。一児の母。
