「どうしてうちの子は、夜になるとグズグズ泣き出すんだろう?」
「さっきまで寝ていたはずなのに、突然泣き出して止まらない…」
新生児期を過ぎたころから始まる夜泣きや寝ぐずり。
多くのママ・パパが一度は経験する育児の悩みではないでしょうか。
そもそも、なぜ赤ちゃんは夜泣きをするのでしょう?
このコラムでは、その原因と今日から試せる対策についてご紹介します。
目次
夜泣き・寝ぐずりはなぜ起きるの?

乳幼児の睡眠は、大人と比べてレム睡眠*の割合が多く、睡眠サイクルも短いため眠りが浅く、まとまって寝ることが難しいのが特徴です。
月齢によって睡眠の特徴は変化しますが、特に生後6か月〜3歳頃までは、睡眠リズムが安定せず、夜中に何度も目を覚ますことも珍しくありません。
*レム睡眠とは睡眠中に急速な眼球運動(Rapid EyeMovement,REM)がみられる状態のこと
原因はさまざま
・昼間の刺激が強すぎた
・寝る直前の環境が騒がしかった
・お腹がすいている/おむつが不快
・眠る直前までスマートフォンやテレビの光を見ていた
・成長による神経の過敏さ(乳児期には「夜泣きのピーク」があります)
実際には「原因がはっきりしない」こともありますが、ほどんどは異常ではなく、赤ちゃんが通る自然な現象です。
ご家庭でできる5つの対策
1. 生活リズムの安定を意識しましょう
毎日同じ時間に起きて、朝日を浴びる。これだけでも体内時計が整いやすくなります。寝る前のルーティン(お風呂→歯磨き→絵本→就寝など)を繰り返すことも効果的です。
2. 入眠環境を整える
室温・湿度・明るさが子どもにとって快適かを見直してみてください。目に見えにくい「暑すぎる寝具」や「小さな音・光」も刺激になります。特に光は睡眠と覚醒のリズムに影響するので、できるだけ暗く静かな環境を用意しましょう。
3. “泣いたらすぐ抱っこ”から一歩だけ工夫を
泣き始めたら、すぐ抱き上げず、まずはやさしい声かけや背中トントンから試してみましょう。自力で再入眠できる力を育てることにもつながります。
4. 昼間の過ごし方を整える
運動不足や刺激の少ない日中を過ごすと、夜になっても眠気が訪れにくくなります。午前中にしっかり体を動かし、午後はゆったり過ごすのが理想です。
5. 保護者自身の休息も最優先に
夜泣きに対応するには、保護者の心身の余裕が不可欠です。睡眠不足の蓄積は育児不安や産後うつの一因にもなり得ます。家族や育児支援サービス、時には専門家に頼ることも、立派な育児の一部です。
夜泣きがあまりに酷いとき、病気の可能性は?
基本的に夜泣きは病気ではありません。ただし、次のような症状がある場合は、医師の診察をおすすめします。
・発熱・咳・鼻水・下痢などの体調不良を伴っている
・一晩中ずっと激しく泣き続ける(3時間以上)
・泣くたびにのけぞるような姿勢になる(てんかんの可能性)
・いびきや呼吸停止のような様子がある(睡眠時無呼吸の可能性)
また、乳児期には「腸重積症」などの緊急対応が必要な病気でも、泣き止まないという症状が出ることがあります。不安な場合は、夜間でも迷わず、まずは#8000(子ども医療電話相談事業)に連絡してください。
最後に:大切なのは「夜泣きはいつか終わる」ということ。
夜泣きに正解の対応はありません。子どもによって、合う方法・落ち着くパターンは本当にさまざまです。
ただし、夜泣きは永遠に続くものではありません。さまざまな対処法を取り入れつつ、ご家族にとって無理のないように赤ちゃんの成長をあたたかく見守ってください。
「どうしても改善しない」「家族が疲弊している」場合や、ご不安な場合は小児科医や助産師に相談しましょう。悩んでいるのは決してあなただけではありません。子育ての中で「わからない」「苦しい」と感じる瞬間こそ、誰かと気持ちを分かち合うことが大切です。
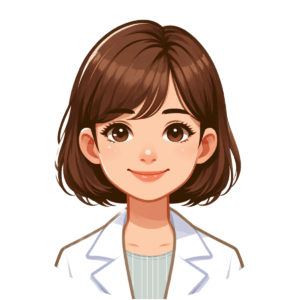
監修医師
ことびあクリニック恵比寿院
石井 知愛子(いしい ちあこ)
医師(ことびあクリニック恵比寿院 非常勤医師 思春期科)
日本小児科学会認定 小児科専門医
東京医科大学を卒業後、同大学の小児科および思春期科で診療と研究に携わり、現在は非常勤医として勤務しています。心と体が大きく変化する思春期のお子さま一人ひとりに寄り添い、丁寧な対話と専門的な視点でサポートしてまいります。

